近所の商店街にあった馴染みの食堂が、先月静かにシャッターを下ろした。
常連だった高齢の男性は、その貼り紙を見てしばらく立ち尽くしたという。
その店は、昔ながらの定食が手頃な値段で食べられる憩いの場だった。
客の多くは近隣に住む年配者で、店主との世間話を楽しみに通っていた。
しかし、近年の人手不足とコスト上昇、さらにデジタル化の波に押されて閉店を決めたそうだ。
「スマホが前提の時代についていけない」と店主はつぶやいた。
大手チェーンが次々に導入するセルフレジやモバイルオーダー。
注文から支払いまで、スマートフォン操作が欠かせない店舗も増えている。
若者にとっては便利な仕組みでも、高齢者にはハードルが高い。
「ボタンがどこにあるのか分からない」「支払い方法が怖い」といった声が絶えない。
紙のメニューや現金払いが当たり前だった時代を知る世代にとって、急激な変化は戸惑いの種だ。
それでも時代の流れに逆らうことは難しい。
行政も「デジタル活用」を掲げ、社会全体がスマホ中心へと移行している。
銀行、病院、公共施設まで、オンライン予約や電子決済が前提となりつつある。
「スマホを持っていないと生活できない」と嘆く声も聞こえる。
中には、機械操作に自信が持てず、外出を控えるようになった人もいるという。
食堂や喫茶店は、そんな人たちにとって貴重な社交の場だった。
しかしデジタル化の波が、その居場所を静かに奪っていく。
ある女性は「レジの前で立ち止まってしまい、後ろの人に申し訳なくて」と語る。
それ以来、混雑するチェーン店を避けるようになったそうだ。
一方で、店舗側にも事情がある。
人件費の高騰、アルバイト不足、そして効率化へのプレッシャー。
非接触型の注文や支払いは、コロナ禍を経て一気に広まった。
感染リスクを減らし、スピードと正確さを保つための手段として定着した。
だが、便利さの裏に取り残される人たちがいる。
誰もが同じスピードで進化できるわけではない。
デジタル格差は、今や世代間の問題を超えて社会全体に広がっている。
スマホを「便利な道具」と捉えるか、「壁」と感じるかで、日常の自由度が変わる。
「昔は人が笑顔で迎えてくれた。それがよかったのに」
そんな声が、消えた店の前で静かにこぼれ落ちる。
一方で、地域の中には新しい工夫を始める店もある。
セルフレジを導入しつつ、スタッフが横で操作を手伝う仕組みだ。
「一緒に押してみましょう」と声をかけることで、少しずつ慣れてもらう。
そうした“人の手によるサポート”が、デジタルと共存する鍵になっている。
また、一部の自治体では「スマホ講習会」を無料で開いている。
写真の撮り方からキャッシュレス決済まで、丁寧に教える取り組みだ。
それでも、「学ぶのが怖い」「失敗したらどうしよう」と不安を抱く人は多い。
年齢を重ねるほど、新しい技術への一歩が重くなる。
誰もがデジタルに順応できる社会を目指すなら、「やさしい設計」が欠かせない。
画面の文字を大きくする、支払い方法を選べる、スタッフが声をかける——。
小さな工夫が、人を安心させる。
そして、その安心が「また来よう」と思わせる。
効率だけを追い求める社会は、心の豊かさを失いかねない。
食事は単なる栄養補給ではなく、人とつながる時間でもある。
シニア世代が居心地よく過ごせる場所は、地域の温度を示すバロメーターだ。
そこに“人のぬくもり”があるかどうかが問われている。
「セルフ」や「非接触」が進むほど、逆に求められるのは「つながり」かもしれない。
便利さと優しさ、その両立がこれからの課題だ。
かつての常連客たちは、今日も新しい居場所を探して歩く。
手の中のスマホを見つめながら、操作にため息をつく。
それでも誰かと温かい食卓を囲みたいという思いは、変わらない。
その願いを叶えるために、社会はもう一度“人の手”を思い出す必要がある。
デジタルの進化は止まらない。
だが、人を思いやる心もまた、進化とともに生きていくべきだ。
「スマホが前提なんて」と戸惑う声に、誰かが優しく寄り添う社会であってほしい。
それが本当の意味での“便利さ”なのかもしれない。



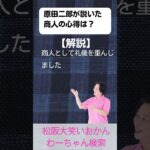

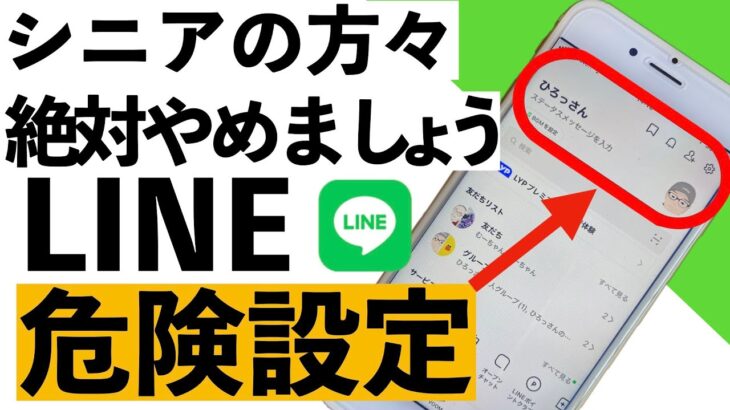
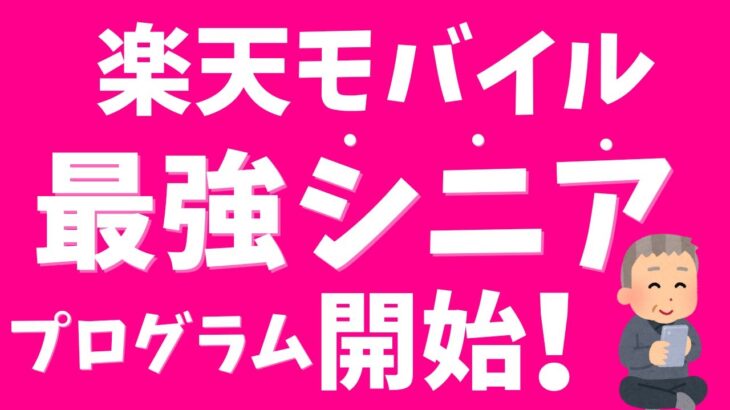

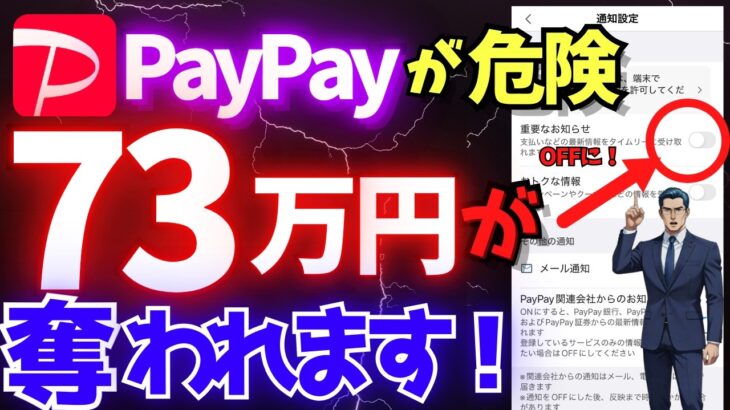
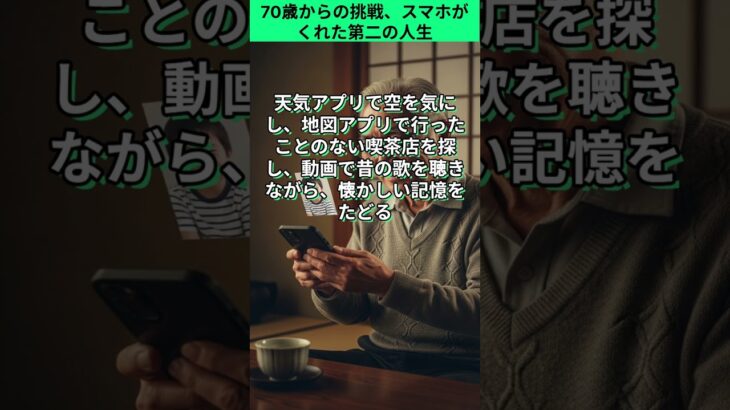
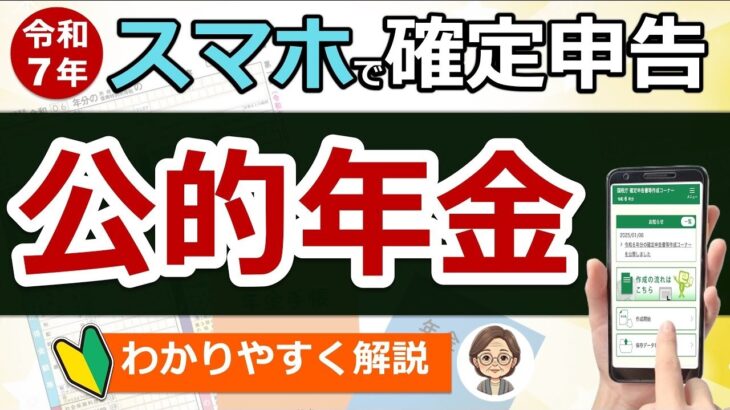
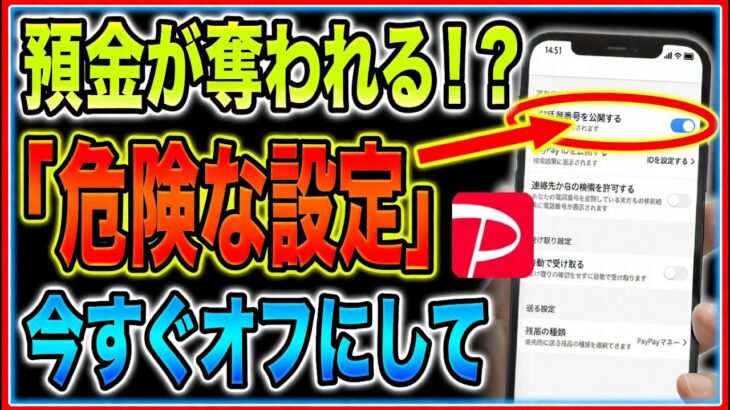
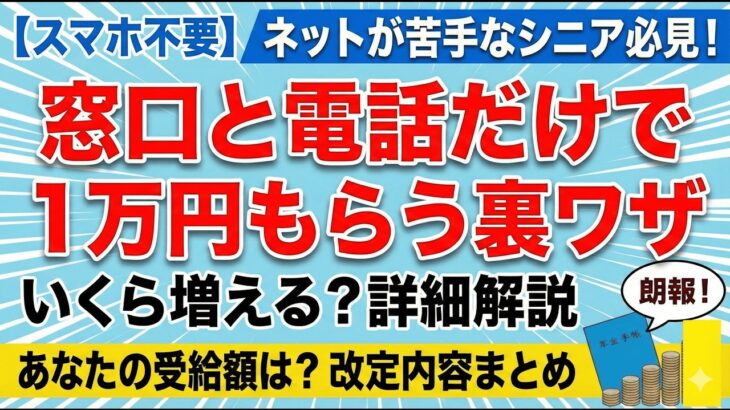
コメントを書く