セルフレジとは、客が自分で商品のバーコードをスキャンし、支払いを済ませるシステムのことだ。コンビニエンスストアやファストフード店を中心に導入が進み、コロナ禍をきっかけに非接触型の決済ニーズが高まったことで、さらに普及が加速した。スマートフォンを使ったQRコード決済や、事前注文アプリの利用も増え、飲食店の多くが「デジタル前提」のサービスに移行している。
しかし、この変化は、すべての客にとって歓迎すべきものではない。総務省の2023年の調査によると、65歳以上のシニア層のうち、スマートフォンを日常的に使いこなしている人は約60%にとどまる。特に70歳以上では、スマートフォンを持っていても、基本的な通話やメール以外の機能を使いこなせない人が多い。こうした背景から、セルフレジやモバイルオーダーの導入は、シニア層にとって大きなハードルとなっている。
例えば、東京都内在住の山田さん(72歳)は、行きつけのファストフード店での体験をこう語る。「以前は店員さんが注文を取ってくれて、気軽におしゃべりしながら食事ができた。でも、今はタッチパネルで注文しないといけないし、支払いもスマホでQRコードを読み取るなんて…。私には難しすぎる。結局、行くのをやめてしまった。」山田さんのように、デジタル機器に不慣れなシニア層にとって、セルフレジは「使いづらい」だけでなく、「疎外感」を感じる要因にもなっている。
2. 行きつけの店を失うシニアたち
飲食店のデジタル化は、シニア層にとって「行きつけの店」を失うきっかけにもなっている。行きつけの店とは、単に食事を提供する場所以上の意味を持つ。そこは地域のコミュニティの場であり、店員とのちょっとした会話や、慣れ親しんだ雰囲気の中で過ごす時間が、シニア層にとって心の支えとなることも多い。
しかし、デジタル化が進むにつれ、こうした「人の温もり」が感じられる場所が減っている。ある調査によると、シニア層の約4割が「デジタル化された店舗に行く頻度が減った」と回答している。特に、ファミリーレストランや喫茶店など、シニア層がよく利用する場所でのセルフレジ導入が、この傾向を加速させている。
神奈川県に住む佐藤さん(68歳)は、近所の喫茶店がモバイルオーダーとセルフレジを導入したことで、足が遠のいたという。「昔は店員さんが笑顔で迎えてくれて、コーヒーを飲みながら世間話をするのが楽しみだった。でも、今はスマホで注文して、機械で支払うだけ。なんだか冷たく感じるし、わざわざ行く気になれない」と語る。佐藤さんのように、デジタル化によって「居心地の良さ」が失われたと感じるシニアは少なくない。
3. なぜ飲食店はデジタル化を進めるのか
飲食店がセルフレジやモバイルオーダーを導入する背景には、いくつかの要因がある。まず、人件費の高騰だ。人手不足が深刻化する中、従業員の雇用コストは年々上昇している。セルフレジを導入することで、注文や会計業務を自動化し、人件費を抑えることができる。また、コロナ禍以降、非接触型のサービスが求められるようになったことも、デジタル化を後押しした。
さらに、若い世代を中心に、スピーディーで効率的なサービスを求める声が高まっている。スマートフォンを使った事前注文は、待ち時間を短縮し、顧客満足度を向上させる効果がある。あるチェーン店の経営者は、「若いお客さんが増える一方で、デジタル対応が遅れると競争に勝てない」と語る。こうした市場の変化に対応するため、飲食店はデジタル化を急いでいる。
しかし、この「効率化」の波は、シニア層を置き去りにするリスクをはらんでいる。デジタル機器に慣れていない人々への配慮が不足している店舗も多く、シニア層が疎外されるケースが増えているのだ。
「スマホが前提なんて…」行きつけ飲食店を失ったシニアも セルフレジに「戸惑う」
- 2025.10.13
- スマホ



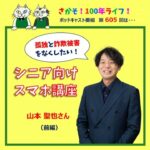
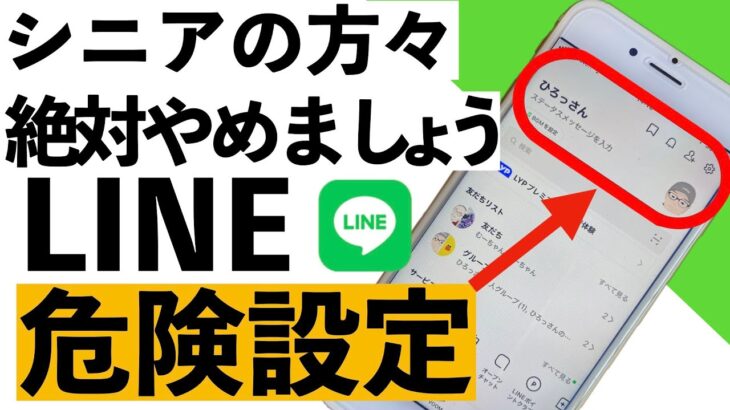

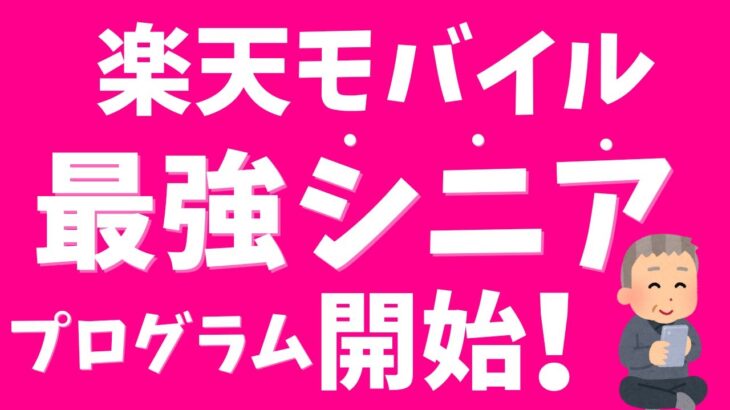





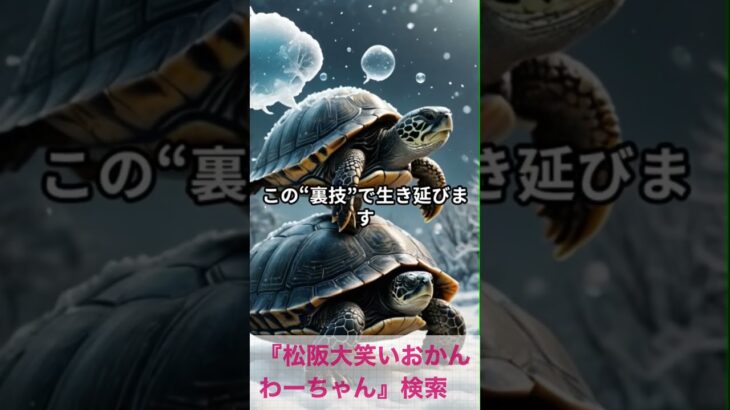
コメントを書く