「墓じまい=簡単な手続き」と思っていませんか?
実際には流れを間違えると、親族トラブルや高額費用に発展し、取り返しのつかない結末を迎えることもあります。
この動画では、墓じまいの基本的な流れから、よくある手続きの落とし穴、お骨の行方で起きやすいトラブルまで徹底解説。
「自分で進めても大丈夫なのか?」「どんな費用がかかるのか?」「家族が揉めないためには?」
そんな不安に答えながら、後悔しない墓じまいのポイントをわかりやすくお伝えします。
▼動画内容
▶ 繰り上げを選びやすい心理トラップと、その裏に潜むリスク
▶ 都市部シニアが直面する生活費の現実と年金格差
▶ 繰り上げ・繰り下げを組み合わせたハイブリッド戦略
📌チャプター(目次)
00:00 オープニング
00:33 制度の心理トラップ
03:

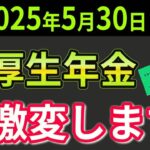



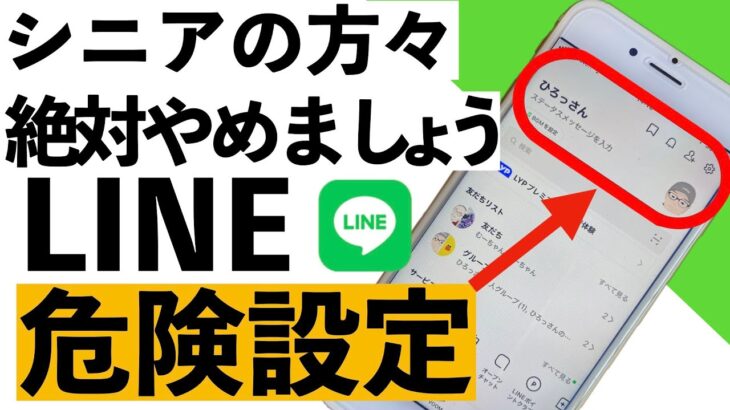
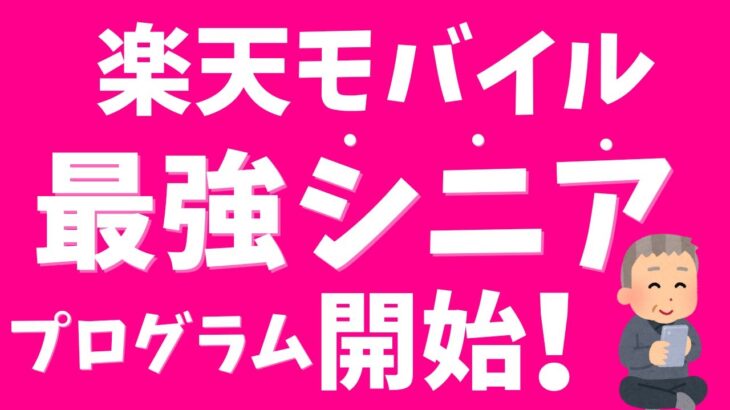

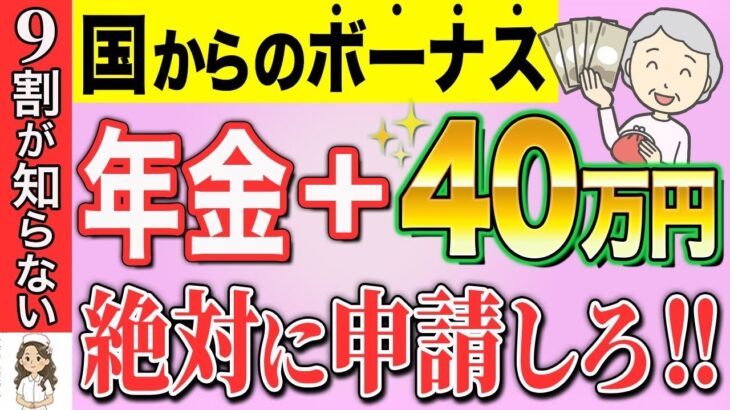
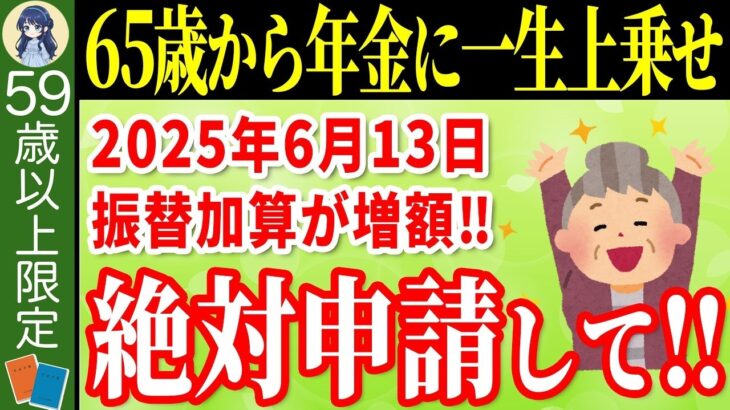
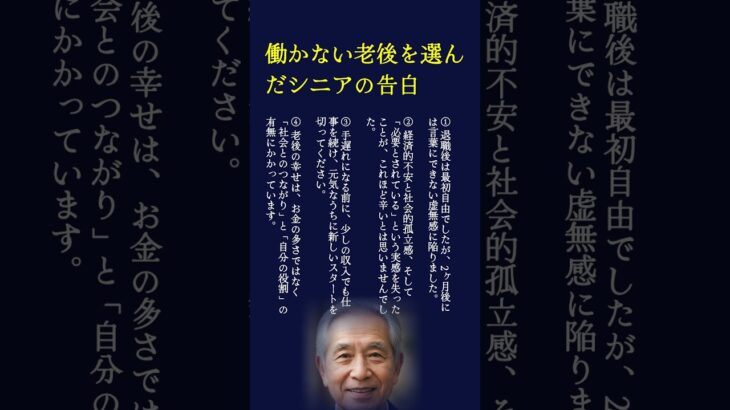

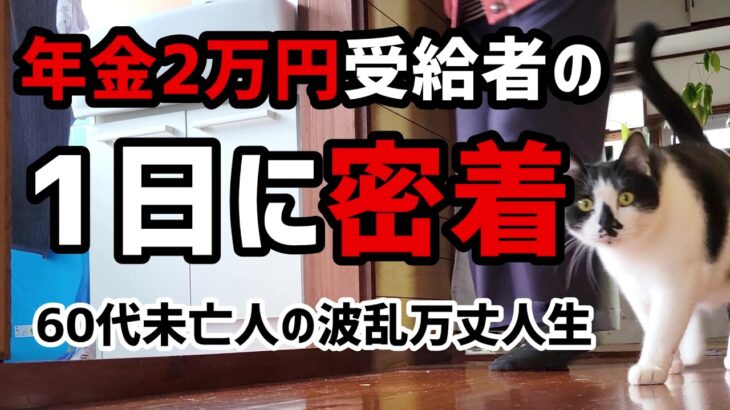
税金保険料などの天引きされるものがありますので、額面の損益分岐点はもっと後になります。わたしはは働いていますが、年金は60歳からもらいはじめ年金と同額を新NISAで、積み立てています。すると、24パーセントの減額より得になりますよ。
繰上げは低年金生活で短命が目標。繰下げは高年金で長寿が目標。
低年金なら乏しい食生活による栄養不足&予防医療費が捻出出来ず病気の悪化で短命の目標は達成出来るかな?
繰下げはそれだけ働く期間が長くなるけど、70歳過ぎて働くよりマシかと
50代で月14万くらい年金もらいはじめた。プラス年金生活者支援給付金。
65歳から月15万円もらえるとして1年180万円。10年で1800万円。これくらいなら退職金ぐらいの金額。だったら先に退職金から使って公的年金は繰り下げればいい。国も推奨している。国の思惑にのるようだが自分は年金を繰り下げるつもり。
一応富裕層ですが、ただ単に動画のネタにしようかと思って62歳から繰り上げしました。
株式の配当金が充分ありますので年金なんてどうでもいいです。
名古屋ですが、持ち家で借金はなく、車は手放したので生活費はそんなにかかりません。
結局何歳から受給を開始しても、60歳から64歳まで受給開始は20年10ヶ月後に、66歳から75歳までは11年11ヶ月後に「損益分岐点を迎える」という原則が年金にはあります
例えば61歳から受給開始した人と70歳から受給開始をした人はそれぞれ81歳10.5ヶ月で同じ金額を受給します
私の経験からですが、60歳そこそこは見た目もカラダも若く、色々遊び恋もできていますので、人生最後の貴重な時間を「労働して寿命を差し出してお金に変える」のはもったいないと思います
65歳で平均的な年金額を受給する人が、62歳までに受給を開始すると「住民税非課税世帯」になる権利を得るので、65歳まではガンガン働いて稼いで貯金や資産を貯めて、65歳以降に老いたり病気になった時に初めて収入を減らすと、自動的に「住民税非課税世帯」としての優遇を得ることができます
この住民税非課税世帯と課税世帯の差はとても大きく、平均的な課税世帯と非課税世帯を比較すると自治体によって異なるところもあるが①住民税が非課税②国保が7割減額③高額医療の自己負担が半額以下④介護保険料の減額⑤介護保険の負担額が減額
入院や手術などがあると平均で非課税世帯が50万円負担の時に課税世帯では200万円以上負担になるケースが多いです
歳をとってから誰でも病気がちになりますが、大病後予後10年生きるとして計算上では年間最低150万円、10年で1500万円の差があり、非課税世帯では「医療補助」の申請ができますが、課税世帯では収入によってそれも叶わず年間数百万の出費が報告されています
人生ってちょっとくらい「出世したぞ」「年収が高いんだぞ」と威張って見せても60歳を超えてからの戦略を間違うと老後破産が待っています
怖いですね